商談時に気を付けること4選
前回の記事で、商談前にやるべきことをご紹介しました。
今回は商談実施の段階です。
自社やサービスに興味を持ってくれている状態の見込み客との商談を実施する際、それまでの準備を台無しにしないよう、商談で気を付けるべきことについてお話しします。
毎回の商談のゴールは何か?
皆さんは、何回の商談を重ねて成約することを想定しているでしょうか?
サービスや単価によって何回の商談が必要になるかは大きな差があり、特にプッシュ型のセールスプロセスで、もともと興味がある人にアプローチすることができたという偶然の場合を除くと、最低でも3回以上の商談を重ねて成約するのが一般的です。
初回の商談では宿題をもらえるように
初回の商談時には
- 自社やサービスの概要の説明
- ヒアリングを実施して次回の商談で提案の機会をいただく約束
を狙うのが一般的です。
稀に初回の商談でよい反応がもらえそうになると、一気にクロージングを狙うこともありますが、焦ってそこで断られたらセカンドチャンスをもらえない可能性が高くなってしまいます。
関係を構築することを優先して、宿題をもらい、次回へとつなげていくことが大切です。
次回の商談日時も、できる限り商談時に決めることを目指しましょう。
営業であり、接客ではない
サービスにもよりますが、伴走型サービスのセールスプロセスにおいては、初回商談時はアイスブレイクの時間を設けるなど、できる限り関係構築を意識することが大切です。
ここで大切なのは接客と営業では考え方が異なるという点です。
相手が欲しいと考えている商品であれば、丁寧に接客をして好感を抱いてもらうことで成約につながりますが、コンサルティングサービスや広告運用などの伴走支援型サービスの場合には、丁寧に接客しているだけではサービス購入後をイメージすることができません。
共にプロジェクトを進めて事業を成長させていくパートナーとして考えた場合に、円滑なコミュニケーションが可能かどうかについても商談時に見定められているのです。
たまに冗談を言って笑い話ができるぐらいの関係ができれば、成約につながりやすく、また成約後のサービス提供の段階でも二人三脚で事業成長のために力を合わせて仕事を進めていけるはずです。
社員の性格などによって多少の差は出てしまうものではありますが、どんな営業活動を目指すのかについては社員間でイメージを共有しておきましょう。
また、2回目、3回目の商談においても、何をゴールとして商談を実施するのかについてあらかじめ決めておきましょう。
見込み客によって、少しずつ差があり予定通りに進むことはむしろ珍しいものですが、それでも毎回の商談のゴールを決めておくことによって、成約までの商談回数や期間に差が出たとしても、ざっくりと同じようなセールスプロセスを経て成約まで進めていくことができるようになります。
つまり、ゴールまでのマイルストーンを定めるということですが、これが決まっていると営業はやりやすくなり、改善策も練りやすくなります。
- 2回目の商談はできる限り対面で実施して、意思決定のプロセスを聞く
- クロージング前の3回目の商談は意思決定者に同席してもらうことを目指す
といった商談時の目標があることによって、成約率を上げていくことが可能になるのです。
自社組織の構築を目指そう
時折、営業代行会社の利用を検討している経営者に会うことがありますが、商談実施まで営業代行会社に実施してもらうということについては私は否定的です。
というのも、実は私も営業代行会社に商談獲得から商談実施までを依頼していたことがあるからです。
私が依頼していたのは営業を得意としている国内有数の有名企業出身者が起ち上げた会社であり、所属している社員も好感を持てる優秀な人ばかりでした。
営業代行を依頼してからすぐに商談を獲得できている様子を見て私も期待していたのですが、結局、成約につながることがないまま、6か月経過後に契約を解消することにしました。
担当してくれていた会社や社員が悪いわけではなく、最後まで対応も気持ちがよかったのですが、やはり成果を見れば取引継続は難しいという判断でした。
営業代行会社に任せず、商談は自社で実施するべきという結論に至ったのはただ経験上うまくいかなかったからというだけではなく、他にもいくつかの理由があります。
事例は知っているが、サービス提供をしていない
本で読んだことを人に話したとして、心に刺さる話ができるでしょうか?
きっと、簡単ではないはずです。
でも、自分が経験したことであれば、感情をこめて相手の心に届く話ができるものです。
営業代行会社に商談を依頼した場合、しっかりとあなたの会社や提供するサービスを学んでくれたとしても、やはりどこか表面的な説明になってしまう可能性が高いのです。
口下手でも構いません。
自身の経験を話すことができれば、見込み客には深く届くものです。
オリジナルの要望にすぐに返答ができない
機能が決まっていて、どの企業にも同じようなサービスを提供する場合には営業代行会社に依頼することを検討してもよいかもしれませんが、BtoBの無形商材の場合には必ずしもそうではありません。
「うちの会社の場合にはこんな機能が欲しいんだけど、そういったことやったことある?」
といった具体的でオリジナルな要望や質問があった場合には、返答に詰まってしまう可能性が高くなります。
1回や2回であれば構いませんが、それまでのコミュニケーションがスムーズであればあるほど、少し込み入った質問をしただけで詰まってしまうと、どうも胡散臭いなと感じられてしまう危険性があるのです。
過去の似たような業界や業種などのサービス提供事例がすぐに出てきたり、それも苦労してサービス提供した話ができるからこそ、信頼やサービスへの期待につながるのがBtoB×無形商材なのです。
営業代行会社は成果につながりやすいサービスに集中したいもの
営業代行会社は多くの場合、伴走型のサービス提供となっており、長期間に渡って関係を継続するほど安定した収益が上がる構造になっています。
販売に貢献できていれば継続率が上がることを考えると、やはり販売しやすいサービスにリソースが集中してしまうのは仕方がないことです。
高額商材の場合には高いインセンティブを用意することによってモチベーションを上げられると考えるかもしれませんが、労力がかかる割に売れなければ結局安価でも安定した成果につながりやすいサービスに集中することになってしまうのです。
自社に営業のリソースが不足している場合には、商談獲得から商談実施までのすべてを営業代行会社に依頼したいと考えるのも無理はありませんし、実際に私もそう考えて実行しました。
でも、オーダーメイドで提供するサービスを営業代行会社が販売する難易度は非常に高いのです。
すべてをまかせてサービス提供に集中したいと考える気持ちもわかりますが、コミュニケーション能力の高い営業代行会社の社員よりも、サービス提供している社員こそが見込み客にとってよい提案ができると私は考えています。
商談が進むにつれて複数人で対応しよう
あなたの会社では、何人で商談対応しているでしょうか?
最初から最後まで1人の社員が対応している企業もあれば、複数人で対応する企業もあるでしょう。
人数に正解があるわけではありませんしサービスにもよりますが、私は基本的には複数人での商談実施をおすすめしています。
営業リソースが少なくて、すべての商談を複数人で実施していくことが難しくても、せめて2回目の商談から、あるいは3回目の商談からというように段階で区切って複数人で対応していく体制を採用することによって様々なメリットがあると考えています。
組織で対応してくれるという安心感
昨今は個人で業務委託の形で仕事を受けるフリーランスや、ひとり社長の企業が増えており、当然、企業もそういった個人や組織に仕事を依頼するケースが増えていることと思います。
実際に私の会社でも、ランディングページのデザインやイラスト、資料作成の業務をフリーランスの方にお願いすることがあり、いつも大変助かっています。
一方で、1人で業務を行っていることに対して、多少のリスクを感じている企業も少なくありません。
私も過去にフリーランスやひとり社長に業務をお願いした際、作業途中で急に辞退されたり、また業務が完了しないまま音信不通になってしまったケースがありました。
優秀な方が非常に多い一方で、企業が業務を外部に依頼する場合、それも組織ではなく1人で業務を行っている人に初めて仕事を依頼する場合には少しリスクを感じることが少なくありません。
もし、業務がスムーズに完了しなかった場合には、1人で業務を行っている人に業務を依頼する意思決定をした人が責任を取ることになってしまうためです。
そのため、私は商談が進むにつれて複数人で対応することをおすすめしています。
実際にずっと複数人で対応していくかどうかの問題ではなく、複数人で対応してくれている状態を見れば、組織としての体制があり、何か問題があったとしても逃げることなく対応してくれるという安心感につながるためです。
営業スキルや事例が共有できる
複数人で対応することによって、1つの成功や失敗を複数人が共有できることになります。
例えば、A企業の商談をXさんとYさんが実施して、うまく商談がまとまったケースがあったとします。
その後、YさんとZさんがB企業の商談を同行営業で対応した場合、A企業でうまくいった事例をB企業に共有しながら提案することが可能になります。
(※会社名など、情報漏洩には十分注意する必要があります)
どのような返答をすれば見込み客の安心感につながったのか、また、業界ごとにどのような課題を抱えていて、どんな施策を求めているのかといった情報を社内で共有しながら対応していくことによって、会社全体の営業スキルを上昇させていくことができます。
商談を1人で対応すると、ノウハウは共有しづらく、トップ営業マンだけがノウハウを抱えていて属人性の高い組織になってしまうというリスクがあります。
トップ営業マンにも他の社員が同行する機会をつくれば、ノウハウやスキルを自然な形で共有することが可能になります。
社員同士でどのように営業を行っているのか情報を共有しましょうと伝えても、失敗事例は共有したくないものです。
複数人で一緒に商談を実施することで、失敗事例の共有も簡単に実現でき、結果として社員の営業スキルとそれに伴う成約率の向上へとつながっていきます。
社員間のコミュニケーションの増加
社員の離職理由の多くは、実はお金(給与面)の問題よりも人間関係の問題が多いと言われています。
でも、会社側が人間関係を円滑にするために何かしらの対応策を考えて実行するのは簡単ではありません。
社員旅行やレクリエーション、飲み会などを実施してコミュニケーションを活発にしようと考える企業もありますが、思い付きで実施しても参加してくれない社員が多い可能性もありますし、失敗すればさらに状況は悪化してしまいます。
基本的な話として、人間関係の悪化の多くはコミュニケーション不足が原因です。
もちろん、コミュニケーションを活発にすることを目的として商談を複数人で実施するわけではありませんが、複数人での商談実施はコミュニケーションの増加につながっていく可能性が高いと考えています。
商談前にコミュニケーションを取る機会が増えますし、案件が決まった際にはお疲れ様会と称した飲み会が開催されるケースもあるかもしれません。
コミュニケーションを取りながら力を合わせて取り組む仕事ができていれば、離職率の低下にもつながっていきます。
以上のように、商談を複数人で対応していくことは、信頼獲得による成約率アップやスキルの共有、離職率低下につながります。
もちろん、社員同士で競争させることで営業成果の最大化を目指すことが有効な施策となる企業もありますが、競争させられていると感じることが仕事へのモチベーションを削いでしまっているケースも少なくないと感じています。
特に昨今の若手社員は、競争よりも共創の考え方に魅力を感じる傾向にあります。
せっかく入社してくれた若手社員が退職することなく、楽しみながら会社に貢献できる環境をつくることができれば、きっと双方にとって幸せな状態となるはずです。
まとめ
今回は、商談時に気を付けるべきことについてお話ししました。
- 毎回の商談のゴールを考える
- 営業であり、接客ではない
- 商談は営業代行会社に任せず、自社で実施する
- 商談が進むにつれて複数人で対応する
すでにご存じの内容も多くあったかと思いますが、知っていることと実行できていることには大きな差があります。
この機会にぜひ今一度ご自身の商談時の対応について振り返ってみてください!
投稿者プロフィール
-
セールスプロセス株式会社代表取締役
新卒でみずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券)に入社。
個人・法人営業に従事し、社長賞を獲得。
退社後、企業専門の出版社を設立して代表取締役に就任。
本をはじめとした出版物でB2B×無形商材を扱う企業の売上アップを支援する、コンサルティング型出版サービスで組織を拡大。
その後、培ってきた営業ノウハウと効果的な営業ツール製作の実績を活かして、『売れる仕組み』の構築を支援するセールスプロセス株式会社を創業。
1985年3月27日生まれ。愛知県名古屋市出身。趣味は野球観戦。
最新の投稿
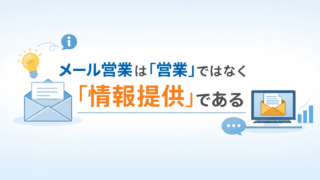 ブログ2026年1月26日メール営業は「営業」ではなく「情報提供」である
ブログ2026年1月26日メール営業は「営業」ではなく「情報提供」である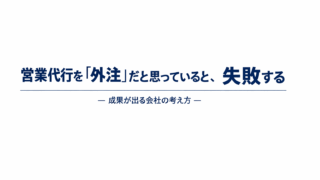 ブログ2026年1月18日営業代行を「外注」だと思っていると、失敗する
ブログ2026年1月18日営業代行を「外注」だと思っていると、失敗する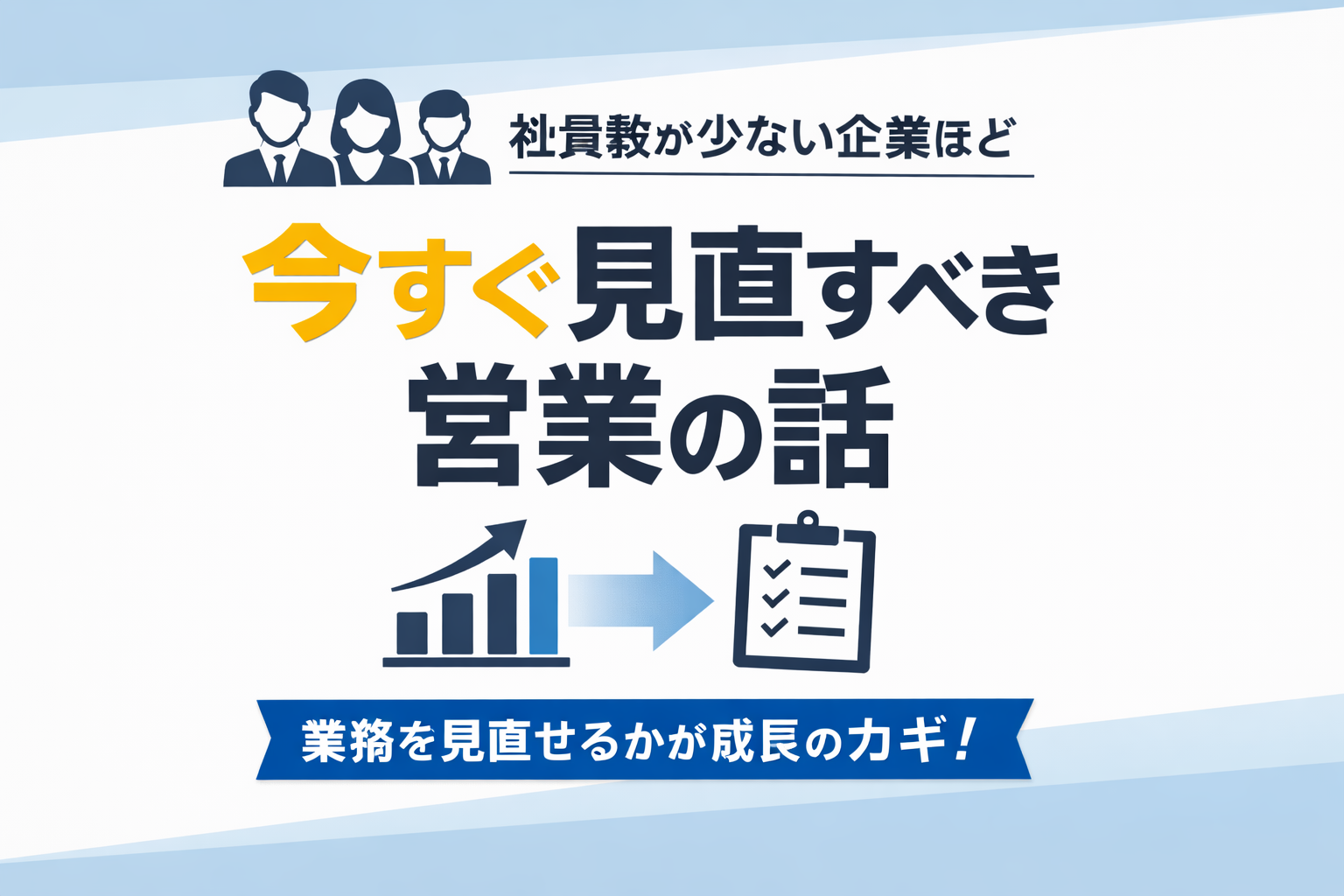 ブログ2026年1月13日社員数が少ない企業ほど、今すぐ見直すべき営業の話
ブログ2026年1月13日社員数が少ない企業ほど、今すぐ見直すべき営業の話 ブログ2026年1月6日テレアポがつらい会社ほど、見直すべき営業手法
ブログ2026年1月6日テレアポがつらい会社ほど、見直すべき営業手法


